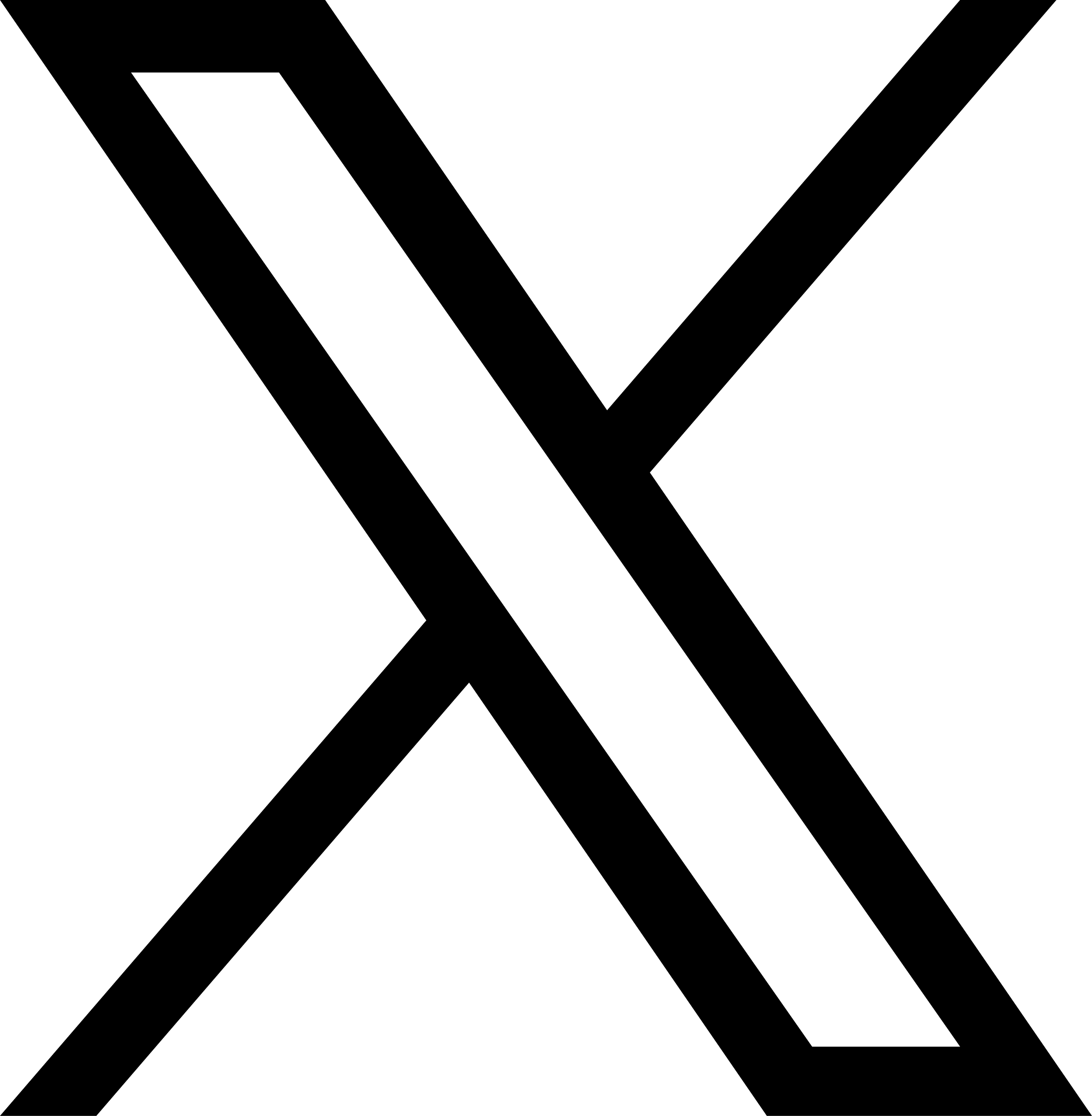門井慶喜『札幌誕生』と現代風古地図「れきちず」がコラボ!地図モード・小説モードなどで時代小説の世界がより一層楽しめる仕掛けが誕生!詳細はこちら
第一話 / 開拓判官 − 島義勇
創成川
元来この札幌の地というのは、木古内や大野ほどには樹木が多くなく、土も硬くなく、農地の造成は比較的むつかしくないほうだったが、問題は水利だった。
川がないのである。(中略)
この札幌にほしいのは、つねに水のたっぷり流れては去る恒常河川なのである。そこで大友亀太郎の最初の仕事は人工水路の開削になった。
その結果がすなわち、
「あれなのですよ。あれ」
と早山が言うのへ、義勇はうなずいて、
「大友堀ですな」
「ええ」
「よくぞ立派になしとげた、とひとまず言えましょうな。もろもろの困難を考えると」
74頁
第二話 / ビー・アンビシャス − 内村鑑三
札幌農学校
入学の日の朝、はじめて札幌農学校の門の前に立って、鑑三は、
「ここは、日本か」
思わず口に出した。
それくらい、目の前の風景は非日本的だった。
まずは塀がない。内地ならば学校だろうが寺社だろうが武家屋敷だろうが、ちょっと大きな建物にはかならず備えられているはずの連続した壁、よそ者をきびしく拒絶する境界面の設置がなく、したがって門も、門というよりは単なる柱を立てた入口にすぎない。
あんまり開放的でありすぎて、鑑三は、かえって不安になった。これがアメリカ流なのだろう。(中略)
そこに立つ校舎群もまた、完全に西洋ふうだった。おそらく本舎なのであろう正面の建物は視界をはみ出すほど横に長く、屋根がたかだかとしていて、その大きな壁がまっ白なペンキで塗られている。
窓はガラス窓で、ペディメントをそなえている。並び方からして平屋だろう。屋根もよくある寄棟ながら、瓦を葺かず、板屋根にやはりペンキを塗っていた。
左右の奥には、それぞれ二階建ての校舎がある。二階建てともなるとその高さはもう学校というより塔のようで、雲に届きそうだった。
128~129頁
第三話 / 人の世の星 − バチラー八重子
ジョン・バチラーの家
さっき見物した赤煉瓦の北海道庁の裏手へまわって、北3条を南へ下り、西7丁目にぶつかるあたりで小さな路地へ入りこむと、木造ながら、まぶしいほどに白く塗られた二階建ての洋館がそびえている。
一種の外国人居住区になっているのか、まわりにもぽつぽつ同種の家が建っているのだが、さすがに玄関のドアまで白というのは他になかった。
243頁
第四話 / 流行作家 − 有島武郎
札幌農学校官舎
明治二十九年(一八九六)九月、十九歳の有島武郎は、札幌農学校予科第五年級に編入学した。
東京生まれ、東京ないし横浜育ち。
それまでの人生で北海道に来たことはなく、そのかわりと言ってはおかしいけれども、両親の媒酌人の甥という人が教授をしていたので、その遠い縁によって、武郎はひとまず北3条西1丁目の彼の官舎に住みこむことになった。
教授の名は、新渡戸稲造。
稲造自身、二十年ほど前におなじ学校で学んでいるので――当時の姓は太田だったが――愛校心もひとしおであり、かつ学生の気持ちがわかるという自負もあったのだろう。
337頁
第五話 / ショートカット − 岡崎文吉
石狩川
そもそも「石狩」の地名の語源はアイヌ語で「激しく曲がる川」を意味するイシカラペッだとする説もあるくらいで、当然、氾濫も多かった。
均せば年に一回以上の頻度。なるほど治水どころの話ではない。たかだか札幌の街ひとつの建設にとりかかれる程度の土木技術では、石狩川には歯が立たないのである。
が、明治の世が進むと、そうも言っていられない。
(中略)
――何とか、しよう。
という機運が、政府および北海道庁の内部で起こった。その機運が、
――やらねば。
という強迫観念にまで高まったのは、明治三十一年(一八九八)九月の大洪水がきっかけだった。(中略)
石狩川は、この年だけで五度目の氾濫だった。これにより石狩平野のほとんどが冠水し、死者・行方不明者は一一二名、被災家屋は約二万戸。
444~445頁